尽きること無い戦闘後の諸事を次々と指示し、こなしながら、ともかくも何よりも優先すべきこと――味方や敵の負傷兵たちを戦場の随所から救出し、治療場へ運び入れること――を完了した頃には、もう日の出も間近い頃だった。
ひとしきり仕事の手を休めて、今、ミカエラとイポーリトは本陣の断崖壁に立ち、昇り来る朝陽の方向を眺めやっていた。
イポーリトの両脇には、己に身を寄せて立つ幼い二人の弟マリアノとフェルナンドがいる。
敵将ガルベスの魔手から必死に母を守ろうとした、愛しくも健気(けなげ)な弟たちの肩を両手で力強く抱き寄せながら、イポーリトは遥か眼前に広がる霊峰群を見つめた。
他方、ミカエラの手の中には、此度の戦場で幾度もイポーリトを護ってくれた黄金の笏杖が、戦塵を丁寧に拭われ磨き上げられて、しっかりと握られている。
そんな彼らが見つめる視界の中で、深い群青色の夜気の底に沈んでいた山々の稜線が、不意に、ひときわ眩い曙光(しょこう)に煌いた。
と見るや、霊峰の峰々を染めゆく光の筋は、まるで溶けた黄金が流れ込んでいくかのように、大地の輪郭いっぱいに広がっていく。
上質な純金を張り詰めたかのように荘厳に輝き渡るアンデスの霊峰や、その隙間を埋める朝露に煌く平原を前にして、四人共、語る言葉を持たず、ただ息を詰め、そこに立ち尽くしていた。

生き延びたこの命、そして、失われた無数の命、火と血に染まり傷ついた大地――それら全てを大きく包み込みながら、朝の太陽は真っ直ぐに天頂指して昇りゆく。
朝陽は、こんなにも美しく、こんなにも物悲しく、そして、こんなにも力強いものであったろうか。
ミカエラも、イポーリトも、目にも心にも眩く沁み入る陽光に、その瞼を細めながら、同じことを思っていた。
此度の勝利は、専門兵も義勇兵も含めた当地のインカ兵たちの並々ならぬ奮闘、シモンの密かな戦略、そして、トゥパク・アマルの要請に応えてくれた村人たちの勇敢な行動――それら全ての力が合わさったからこそ、達成し得たものなのだ。
もちろん、インカの神々の篤い庇護や武運、離れた地からも力や思いを送り続けてくれた兵や人々のおかげでもある。
(そのどれかひとつでも欠けていたら、今、こうして新しい日の出を見ることなどできなかったであろう。
いや、生き残った者よりも、この曙光を見ることのかなわなかった者たちの方が多いのだ……!)
ミカエラは、朝陽を反射して直視できぬほどの輝きを放っている黄金の笏杖を、いっそう強く握り締めた。

イポーリトもまた、降り注ぐ光とその暖かさを全身に感じ取りながら、血痕の残る唇をきつく噛み締める。
無意識に力のこもる兄の手の感触を肩に感じ取りながら、マリアノとフェルナンドも、若々しさに一回り精悍さを増した目元を鋭くした。
その傍らでミカエラは睫毛を伏せ、それから、また決然と双瞼を見開く。
そして、四人は、霊峰の遥か先に広がっているであろう大海原の方角へと、研ぎ澄まされた横顔を向けた。
当地の本陣戦がひとつ勝利したからといって、まだ此度の戦さ全体の勝敗の行方が決まったわけではない。
国中の戦いは、激しさを増しながら、今も現在進行形で続いているのだ。
あのアレッチェ率いるスペイン軍主力部隊や英国艦隊とトゥパク・アマル軍との決戦も、目前に迫っている。
(今度はあなたの番ね――トゥパク…!!)
遥かなる大海原の方角へと視線を馳せ続けるミカエラを、息子たちを、そして、本陣全体を、光の強さを増しながら昇りゆく太陽が燦然と照らし出していた。

こうしてアンデス高地の一角でミカエラやイポーリトたちの戦いが一つの幕を下ろし、インカ軍の勝利という朗報が、遥かに離れた沿岸部のトゥパク・アマル陣営にも届こうとしていた。
夜目も鍛えられたミカエラの伝令鳥が、空が白みかけるよりも早く、トゥパク・アマルの陣営を目指して放たれていたのだった。
だが、その伝令鳥がトゥパク・アマルの元に届くよりも先に――恐らく、彼の陣営の誰よりも早く、本陣の勝利を悟っていた者がいた。
迫り来る英国艦隊やアレッチェ率いるスペイン軍主力部隊との決戦を目前に控え、ささやかなまどろみの中にある広大な野営場。
その片隅で、まだ夜明け前の青く透明な空を見上げて立つ細いシルエット。
華奢な肩では長いおさげが潮風に舞い、ほっそりとした足首がのぞくスカートの裾がパタパタと音をたててはためいている。
コイユールは、高鳴る胸の鼓動を感じながら、硬く閉じていた瞼を薄っすらと見開いた。
そして、その澄んだ黒い瞳を、白く瞬く明けの明星に真っ直ぐ向けた。

星の清浄な煌きが、目にも、心にも染み渡る。
コイユールは、心に差し込んだ光の感触を確かめるかのように、祈りのために組み合わせていた両手をほどき、片手をそっと胸に当ててみる。
それから、そこに宿る生気に満ちた力強い感覚に、じっと意識を集中した。
不意に、目元から、ツッと光る雫が零れ落ちる。
それを細い指先で拭うと、今度は大きく表情を輝かせた。
(サンガララの本陣の戦いが終わった!
ミカエラ様、皇子様……!!)
実は、トゥパク・アマルは、重側近や幹部たちを除いて、当陣営の兵たちには此度の本陣への敵襲について敢えて伝えてはいなかった。
この反乱の成否を決めることになるであろう重要な決戦を目前に控えた今、兵たちの不安を煽るようなことは如何なることも避けたい、というトゥパク・アマルの考えによるものであった。
それ故、当然ながら、末端の一義勇兵にすぎぬコイユールは、他の義勇兵たちと同様、本陣で起こっていることを聞かされてはいなかった。
しかし、僅かながらも超常的な力を持つ彼女は、誰に告げられずとも、ミカエラやイポーリトたちが直面していた危機的状況を直観的に悟っていたのだった。
トゥパク・アマルからも遠く離れ、援軍も期待できぬ本陣のミカエラや兵たちが、どのような思いをし、どのような戦いを強いられているのか、それを想像すると、コイユールの魂は心底から震えた。
潮風の吹きすさぶ夜の外気の中で、一晩中、インカの神々に懸命に祈りを捧げ続けた体は、すっかり凍えている。
たが、今は、そんな彼女の全身も、心も、神々しく清々しい輝きに満ちていた。
冷気の中にもかかわらず、その淡い褐色の頬を紅潮させながら、くっきりとした目元を眩げに細める。

その時、白みゆく天空から降り注ぐ流星たちの一つが、地平線に消えることなく、陣営の上空を高速でよぎっていった。
コイユールはハッと息を詰めて、その光の軌跡を追う。
遥かな視線の先で、瞬間、それは鳥の翼らしい輪郭をあらわし、そのままトゥパク・アマルの天幕の方角へとまっしぐらに飛び去っていた。
(あれは…!
きっと、ミカエラ様の伝令鳥だわ!!)
改めてコイユールの胸は熱く込み上げる。
日が高くなる頃には、今度は自分たちが厳しい戦闘に巻き込まれているかもしれない。
それでも、今、この瞬間は、この尊い勝利を噛み締めていたい。
(あの伝令鳥のもたらす朗報を知ったら、トゥパク・アマル様もどんなに安堵されるかしら)
本陣が今回のような事態に陥り、トゥパク・アマルが、ミカエラや皇子たちはもとより本陣の兵たちをどれほど強く案じ、自らを激しく責め苛んでいたか、そのことも痛いほど感じ取っていたコイユールは深く息をついた。
彼女の口元から安堵と歓喜の囁きが漏れる。
「ああ、神様、感謝します!」
その言葉と重なるように、空の方から、朝陽を浴びてキラキラ光る小さな何かが、フワリと目の前に舞い降りてきた。
反射的に手の平を広げて、そっと、それを受け留める。
「羽…!」
軽やかで柔らかな羽毛の感触を手の平に感じ取りながら、コイユールは瞳を瞬かせた。
(もしかしたら今の伝令鳥の羽かしら?)
その羽をそっと両手の中に包み込むと、えもいわれぬ優しい温かさに心が満たされる。

ありがとう!――飛び去る伝令鳥に心の中で微笑み、コイユールは、そっとハンカチに羽を包んだ。
それを懐にしまいながら、彼女の瞳が輝く。
(もし戦いが始まる前にまた会えたら、この羽、アンドレスに渡そう!
勝利の吉報を運んできてくれた伝令鳥の羽だなんて、とっても縁起がいいもの)
そんなふうに思ってから、はたと我に返って、また頬を赤らめる。
本陣のことが一段落して安堵したかと思えば、気持ちは瞬く間に愛しい人の元へと舞い戻ってしまう。
そんな自分に呆れながらも、今度は小さく溜息をついた。
(でも、アンドレスは、もう昨日のうちに軍を率いて出陣したって聞いたわ。
スペイン軍の砦にはたくさんの大砲が備えてあるから、それを何とかするために、敵軍の傍に潜んで進撃の機会を狙うんだって…)
もちろんアンドレスから直接にそのような話を聞かされていたわけではないが、仲間の義勇兵たちが話している内容を断片的に耳にしていたのだった。
コイユールは固唾を呑んで、顔を曇らせた。
(これから日が高くなれば英国艦隊が押し寄せてきて、インカ軍もスペイン軍も戦いを始めてしまうに違いないわ。
このまま決戦が始まってしまったら、もう、せっかくのこの羽だって、きっとアンドレスに渡す機会なんて無い)
急激に強い不安が込み上げてきて、懐にしまった羽を、ギュッ、と衣服の上から押さえ込む。
いっそのこと、このまま夜が明けなければいいのに!!――今しがたまでの笑みは早くも影を潜め、コイユールは瞼を震わせながら、ますます青みを増しゆく朝の天空を見つめ続けた。
かくして、コイユールが思いを馳せるアンドレスもまた、身を切られる思いで一夜を明かしていた。
海底のような深蒼色に霞む早朝の森林地帯で、大木の陰に身を隠しながら空を見上げて立つ一人の若者を、明けの明星が静かに照らしている。
大地から真っ直ぐに伸び立つ若木のように高く伸びた長身は、幾つもの戦火を潜り抜けていっそう逞しく鍛えられ、漆黒の短マントを翻す姿は若き日のトゥパク・アマルを彷彿とさせる。
混血児らしい精巧さと精悍さを兼ね備えた輪郭を縁取る淡色の髪が、梢の葉を揺らす朝風に柔らかくなびいている。
遠目からは森の精霊に見初められそうな端麗な姿であったが、実際には、彼の表情は深い苦悩に満ちていた。

このアンドレスは、自軍を率いて昨日のうちにトゥパク・アマル陣営を出陣し、アレッチェ率いるスペイン軍主力部隊の砦の傍に身を潜めていた。
昨日のうちにあるかと思われた英国艦隊の到来が遅れており、とはいえ、いつ何が起こるか分からぬ状況の中、アンドレス軍も臨戦態勢を敷いたまま、昨夜はその場にて野営をしていた。
そのような最中、トゥパク・アマルからの密使によって、サンガララの本陣に敵軍が迫っていることを知らされたのだった。
トゥパク・アマルの命を受けるまでもなく、彼もまた、重要な戦いを目前に控えた自軍の兵たちに大きな動揺をきたすことの無きよう、その悪夢のような知らせを己の心の内におさめるしかなかった。
だが、ミカエラや皇子たち、そして、本陣の兵たちのことを思うと、文字通り身を引き裂かれる思いであった。
すぐにも援軍を率いて本陣にとって返したいと、幾度、本気で思ったことだろう。
しかし、いつ当地で戦闘の火蓋が切られるか分からぬ状況下で、この場を離れることは許されなかった。
しかも、この沿岸部からアンデス高地の本陣までは長大な距離の隔たりがあり、どれほど駿馬を馳せようとも、本陣での戦いに間に合わぬどころか戦闘が終結した頃にさえ辿り着けはしなかったであろう。
そして、今も、本陣戦の行方を何も知ることのままならぬまま、矢も楯もたまらぬ心境で、ただひたすら本陣のインカ軍の武運を念じ続けていたのだった。
実の弟にも等しく思っているイポーリトやマリアノ、フェルナンドの姿が脳裏に浮かび、いっそうアンドレスの心を締め付けた。
幼くして反乱の渦中に巻き込まれることとなったトゥパク・アマルの息子たち。
長男イポーリトでさえ、実際には、まだ年端もいかぬ少年にすぎない。
自分がイポーリトほどの年齢だった頃には、反乱も幕を開けてはおらず、クスコの神学校で学科や競技の授業に精を出す日々を送っていたのだ。

スペイン人教師が目を光らせる寄宿学校の中で閉塞感や反発心はあったものの、それでも、今にして思えば、気ままな学生生活に違いなかった。
その上、あの当時の自分は、まともな剣の振り方、いや、握り方ひとつ知らなかった。
それに対して、今のイポーリトたちは…――!!
アンドレスは苦しげに眉根を寄せた。
(ミカエラ様が総指揮を執っていらっしゃるとして、ベルムデス殿以外に主だった重側近のいない本陣で、他に指揮を執る可能性があるとしたら…。
まさか、イポーリト様が前線に立って……?!)
一晩中ぐるぐる頭を巡り続けた戦慄に、再び胸を押し潰される。
震える瞼の隙間から見上げる空を、だが、不意にその時、流星と共に一筋の眩い光が流れた。
と思いきや、その光は、こちらに向かって高速で飛来してくるではないか!
(あれは、多分、ミカエラ様の伝令鳥だ!!)
即座に直観し、アンドレスは、思わず木陰から大きく身を乗り出した。
その瞬間、敵陣の視界から身を隠していることさえ忘れて、伝令鳥の飛跡を夢中で目で追いかける。
射し込みだしたばかりの瑞々しい朝陽を翼に反射させながら、その鳥は、光のような速さで彼の遥か頭上を通過していった。
そして、そのままトゥパク・アマル陣営の方角にまっしぐらに飛び去ると、陣営上空を大きく一巡してから、今度は猛烈な勢いで急降下し始めた。
きっと、あの伝令鳥は、トゥパク・アマルの姿を下界に見出したのに相違ない。
(ああ…!!
戦さの結果は?!)
ミカエラからの伝文に目を通すトゥパク・アマルの姿を思い描きながら、アンドレスは激しく波打つ鼓動を抑えきれず、ギュッと胸元を押さえ込む。
すぐにもそちらに馬を飛ばしたい衝動を必死で堪えながら、いっそう強く胸を押さえた指先に、その時、ふと、滑らかな感触が伝わってきた。
ハッとして、その感触の主を胸元から引き出してみる。
それは、彼の首から提げられたグランデーロの小瓶であった。
今朝一番の曙光を浴びて、彼の手の中で、小さなガラス瓶に詰められた美しい鉱石や種子たちが、キラキラと繊細な輝きを放っている。
(コイユール……!)
この愛らしくも強力なお守りの贈り主を思いながら、アンドレスは目を細め、自分の心に囁いた。
(そうだな、落ち着かなければいけないな。
俺は、すぐに気持ちが急いて、熱くなったり、突っ走ったり…。
それで、どれだけ失敗も重ねてきたことか)
彼は改めて木陰に身を隠すと、大きく早朝の空気を吸い込んだ。
森の芳しい薫りが、清々しく全身を満たしていく。
正直、まだ著しく逸る思いは拭い切れなかったが、それでも、手の平に乗せたグランデーロの輝きを見つめていると、不思議と気持ちが凪いでくるのだった。
(本陣戦の結果は、トゥパク・アマル様が、ほどなく知らせてくれるだろう。
それに、ミカエラ様の伝令鳥は、あんなに力強く飛翔していたじゃないか!)

アンドレスは、今一度、伝令鳥の飛び去った方角に目をやった。
逞しい羽ばたきの残像が瞼の裏に甦り、彼の横顔にも力が宿る。
――きっと、いい知らせに違いない!
信じて待とう。
そして、今は、己の為すべきことに集中するんだ!!
こうしてアンドレスやコイユールが伝令鳥の飛来に様々な思いを馳せていた頃、正確には、その少し前だが、当のトゥパク・アマルは、どうしていたであろうか。
夜明け前の闇が最も深い頃、彼は、書斎風にしつらえられた己の天幕の中で、堅固な机を前に座し、じっと瞼を閉じていた。
休息をとらせるために側近たちも各自の天幕に戻らせていたため、今、その天幕の中にいるのは彼一人であった。

いつ戦端が切られても即応できるよう漆黒の戦闘衣に身を包んだまま、黙って目を閉じているその姿は、一見、仮眠をとっているようにも見える。
しかし、トゥパク・アマルの意識は清明に研ぎ澄まされていた。
いついかなる時も、当陣営のみならず、国全体に意識を広げている彼であるが、今、この瞬間は、彼の意識の多くはミカエラたちが戦っているであろう本陣へと集中していた。
机上には、重厚な長剣が鞘を抜かれて置かれ、その柄には彼の右手が添えられている。
――まるで己自身も、本陣の兵たちと共に戦っているかのように。
夜明け前の薄暗い天幕の中で、ガッシリと引き締まった長身を椅子の背に軽くあずけ、机上の長剣を握るトゥパク・アマル。
その全身からは、青白い光の微粒子が放たれているかのようにさえ見える。
その時、彼の目が、ハッと見開かれた。
即座に立ち上がり、剣を鞘に収めて腰に佩(は)かせると、足早に天幕出口へと向かう。
そして、敏速な動作で出口の垂れ布をめくり、まだ薄暗い外界へと踏み出していった。
不意に姿を現したトゥパク・アマルに、警護にあたっていた衛兵たちが、すかさず礼を払って道を開ける。
「おはようございます、陛下!!」
「おはよう」
軽く会釈を返して天幕を離れていくトゥパク・アマルに、このような夜明け前に何か異変でも?!という真剣な眼差しを向けてくる衛兵たちに、彼は静かな声で応じた。
「案ずるな。
少しその辺りを歩いてくる。
日が昇れば、今日は長い一日になろう。
そなたたちは、もう少し体を休めていなさい」
そう言って衛兵たちの間を通り抜け、朝露に濡れた大地を踏みしめる彼の足は、波濤の打ち寄せる断崖壁に向かっていく。

冷たい潮風に長髪をなぶらせながら振り仰ぐ天空は、やっと微かな曙光に彩られ始めたばかりである。
海側から山側へと視線を移し、次第に明るさを増しゆく空を見つめていた彼の視界の中に、やがて、こちらに向かって飛来する一筋の光が飛び込んだ。
(来たか――!!)
光の軌跡は、近づくにつれて、飛翔する鳥の輪郭を鮮明にあらわしていく。
翼に曙光を浴びて自ら光を放っているかのように見えるその姿に、トゥパク・アマルは切れ長の目を眩げに細めた。
ほどなく鳥は陣営上空に到達し、大きくひとつ旋回してから、すぐに地上で待ち受けるトゥパク・アマルの姿を見つけたらしく、そちらに急降下し始めた。
長距離を飛行して疲弊しているに相違ないのに、己の方に向かって、誇らしげにさえ見える力強い羽ばたきで降下してくる伝令鳥の姿に、トゥパク・アマルは吉報を直観した。
そう思えばなおのこと、待ちきれぬ思いに駆り立てられずにはいられない。
彼は、己の方に勢い良く向かいくる鳥の進路へ大きく踏み出すと、高々と腕を掲げ上げた。

バサバサッと、羽音高く飛び込んできた伝令鳥を、褐色の逞しい腕が、ガッシ、と受け留める。
「長き道程、ご苦労であった」
己の腕の上で、まだバサリバサリと大きく翼を羽ばたかせている鳥の方へ語りかけると、やがて、鳥は、ゆっくりとその強靭な翼をたたんでいく。
片腕に鋭い爪の感触と重量を感じ取りながら、トゥパク・アマルのもう片手は、鳥の足に巻きつけられている布を即座にほどいた。
と同時に、そこに記された伝文に素早く目を走らせる。
たちまち光の射しゆくトゥパク・アマルの横顔に、いつから背後に控えていたのか、護衛のビルカパサも、その屈強な体躯を低めながら思わず表情を明るくした。
「トゥパク・アマル様、良い知らせでございましょうか?」
声の方に、トゥパク・アマルもサッと視線を走らせる。
「ビルカパサか。
そなたまで早々と起こして、すまぬ。
まだ休んでいて良いものを」
「いえ。
それより、陛下、本陣からの知らせは如何に?
そのご様子ですと、吉報でございましょうか?」
常に感情統制のいき届いたビルカパサでさえ、今は、その太い声音に明らかに興奮を滲ませている。
そんな相手に、トゥパク・アマルも深い感慨を宿した眼差しで、力強く頷いた。
煌きを増す明け初めの曙光が、彼の秀麗な輪郭を黄金色に縁取っている。
「本陣戦は、インカ側の勝利に終わったとのこと。
ビルカパサ、そなたには、ずいぶん気を揉ませてしまったが」
「めっそうもございませぬ」
ビルカパサは決然と首を振り、「それよりも、ミカエラ様や皇子様方はご無事であられましょうか?」と、その頑健な身を大きく乗り出した。

「ああ。
ミカエラも息子たちも無事でいるとのこと」
さすがのトゥパク・アマルも歓喜を隠せぬらしき明るい声音に、ビルカパサも野性的な面持ちを大きく輝かせた。
「それは何よりでございます。
陛下の策が、功を奏したのでございましょう!」
一方、トゥパク・アマルは、己の腕の上で翼を休めている伝令鳥の姿を見下ろしながら、思慮深げな横顔になって目元を細めた。
「村人たちの果敢な協力は実に頼もしいことであったが、あの策で講ずることができたのは、あくまで偽装の戦力にすぎなかった。
何と言っても、この勝利、優勢な敵軍にも怯まず戦火を交えた本陣の兵たちの、並々ならぬ戦いぶりによるところが大きい」
ひとしきりトゥパク・アマルの腕の上で休息したためか、早くも伝令鳥は、また力強く翼を羽ばたかせ始めている。
「もう行ってもよいのか?」とでも言いたげな顔つきで、小首をかしげながら己を見上げる鳥の仕草に、トゥパク・アマルは静かに微笑んだ。
「ああ、行ってもかまわない。
わたしからの返信は後ほど用意いたそう。
今は、自由にしてくるがよい」
まるで主の言葉を解したかのように、朝食でも摂りに行ったのか、意気揚々と大海原の方に飛び去った鳥の姿に、ビルカパサは感心したように目を奪われた。

が、ほどなくトゥパク・アマルの沈着な声音が、再び彼の耳に響き始めた。
「わたしの要請に応えてくれたあの『援軍』が山麓に到来した時、本陣に攻め入っていた敵軍がもっと冷静で、あれが偽装の援軍であることを見破っていたら、どうなっていたと思う?」
「それは……」
言葉を濁したビルカパサに黙って頷き、それから、飛び去った伝令鳥の飛跡を追うように遠く視線を馳せてから、トゥパク・アマルがまた続けていく。
「もし敵が偽装を見破っていたなら、わたしには、もう為す術は無かった。
だが、実際には、敵は偽装を見破ることができなかった。
つまりは、あの時、敵軍は、それほどに動揺、あるいは、混乱した状態に既に追いやられていたということだ。
そこまで敵を追い込んでいた本陣の兵たちの戦いぶり、実に天晴れであった」
「本陣の皆々、よほど士気高く臨んだのでございましょう。
あのミカエラ様の指揮下なれば――」
そう言いさして、ビルカパサは、ハッと大きく息を詰めた。
「まさか!
イポーリト様が兵を率いたのでは…!」
「まさしく」
朝日の光芒に煌く大海原の果てに向いたまま答えるトゥパク・アマルの面差しには、厳然とした険しさと深い安堵との両方が複雑に絡み合いながら宿っているように見える。

「そなたが察している通り、白兵戦を挑んだ主力部隊をあのイポーリトが率いたという」
「なんと……!」
ビルカパサも驚嘆して、一瞬、言葉を呑む。
しかし、すぐに大きく身を乗り出した。
「それは、なんという頼もしきことでございましょうか。
陛下の分身にも等しきイポーリト様のご出陣ともなれば、劣勢であった我が軍にとっては、この上なき力の源となられたことでございましょう!」
勇猛な表情を輝かせるビルカパサを背後にしたまま、トゥパク・アマルは黙って目を伏せた。
イポーリトが前線に立ったことはミカエラの伝文にも簡潔に書き添えられてはいたが、それを読むまでもなく、トゥパク・アマルはそのことを早々に直観していた。
昨夕から今朝方まで、本陣に意識を集中し続けた彼の心は、実際に、あの山岳の戦場を馳せ、剣と笏杖を手に敵と戦い、幾度もイポーリトの盾となって彼を護った。

己を呼ぶイポーリトの声さえ、鮮明に聞こえたと感じたほどだった。
まともな戦闘経験なぞ皆無の若年の息子が、あのような血生臭く凄惨な戦場に臨み、何度も打ちひしがれながらも、兵たちと共に最後まで必死に戦い抜いた――そのことを思うと、胸が熱く込み上げずにはいられない。
しかも、奇跡的にも、イポーリトは殆ど無傷で生き延びたのだ。
そのことを神にどこまでも感謝せずにはいられなかった。
だが、その一方で、総指揮官としての彼の思いは、また別のところにあった。
瞳を見開いたトゥパク・アマルの表情は、厳格さを増していく。
「わたしとて、此度のイポーリトが見せた気概を認めぬわけではない。
兵力で著しく劣り退路も無き逼迫した戦場であったればなおのこと、そなたが申すように、イポーリトが表に立ったことで兵の士気を高めた面もあったであろう。
しかし、実際には、イポーリトは、技量も、器も、まだ軍を率いるには未熟すぎる。
周りの者たちが、どれほど犠牲となり、あれを護り、支えてくれたことか。
一歩まかり間違えば、今頃は敵の手中に落ちていても何の不思議もなかった。

国中の戦況が緊迫感を増し、ひとつの過ちさえ致命的になりかねぬこの時に、敵の餌食となりに敢えて自ら出向いて行ったにも等しい。
結果が幸運にも吉と出たから良かったようなものの、イポーリトの出陣は実に際どい賭けであった。
あのミカエラが、そのような危うい判断をくだすとは。
それほどの厳しき状況にまで本陣の兵たちを追いやってしまった、このわたしの責任はあまりに重大だ」
「トゥパク・アマル様、そのような……」
「それに、詳しい経緯はまだ分からぬが、あのシモン殿の加勢も大きかったと、ここに記されている」
「シモン殿が?
あ、もしや、トゥパク・アマル様に面会に来られた際の書状を持って、ミカエラ様の元にいらしていたのでしょうか?」
またハッと顔を上げたビルカパサに、トゥパク・アマルも「うむ」と頷く。
「シモン殿がここに面会に訪れた際、そなたの言うように、彼の率いる革命軍への通行証を融通するよう、ミカエラに書状を綴ったものを渡していたゆえ。
恐らく、シモン殿の行軍の途上で、通行証が入り用になり、わたしからの書状を持ってミカエラの元に立ち寄っていたのであろう。
敵襲を知って即座に立ち去ることもできたろうに、劣勢な本陣のインカ軍を見放さず、戦いを援護してくれた彼には感謝の念を禁じえぬ。
このミカエラの報告でも、あの者の講じた策が敵兵の動揺を誘ったとある。
おかげで、ミカエラたちにとっては、願ってもない味方を得た結果となった」
猛々しい目で頷くビルカパサの面持ちに応えてから、再びミカエラの伝文に視線を向けたトゥパク・アマルの横顔は、さらに厳粛さを増していく。

「多くの者の力が合わさり、幸いにもギリギリのところで勝利を手にはしたものの、敵味方共に、この戦いで犠牲になった者たちの甚大さは、筆舌に尽くしがたきものであろう。
本陣には、専門兵はもとより、志高き義勇兵たちも、多数、参集していた。
まだ訓練半ばの義勇兵たちさえも勇敢に戦って、結果、多くの者がその尊き命を落とした。
このような形で甚だしい数の人命を奪い去ってしまったこと、悔いても、悔い切れぬ」
そう言って言葉を切ったトゥパク・アマルの後ろ姿に、ビルカパサは厳つい身を低めて跪き、黙って深々と礼を払った。
急激な戦線の拡大と共に本陣が手薄になり、結果、敵につけいる隙を与えてしまった――そのことで自身を強く責め苛んでいる主の心中をよく察しているだけに、ビルカパサには不用意な言葉を継ぐことはできなかった。幾ばくかの沈黙が流れた。
が、やがて、足元の崖下で激しく打ち砕ける波濤を見つめていたトゥパク・アマルが、ゆっくり顔を上げた。
険しい光を湛えた彼の視線は、そのまま蒼溟(そうめい)たる水平線をなぞりながら、次第に、スペイン軍主力部隊の陣営へと移っていく。
その敵方の陣営は、インカ軍が陣を敷くこの断崖部から暫しの距離を隔てた高台に聳え立つ堅固な砦の中にある。
此度の英国艦隊のごとき外敵の襲来に備えて、この反乱が幕を開けるよりもずっと以前から築かれていたその重厚な砦には、遠目からも生々しく見て取れる多数の砲門が備えられている。
まるで獰猛な怪物が瞼を閉じているかのように、今は不気味に固く閉ざされたそれらの砲門の陰では、入念に手入れされた砲身が火を噴く瞬間を虎視眈々と待ち侘びていることであろう。

切れ長の目元を鋭く聳やかせ、厳めしい眼光でそちらを見据えるトゥパク・アマルの全身に、早朝の強風が吹きつけ、彼の漆黒のマントと長髪を荒々しく天に巻き上げた。
強い潮風をはらんでバサバサと音を立てるマントをさらに大きく翻し、トゥパク・アマルは、体ごと敵の砦の方へと向き直る。
「おおかた、今頃は、あの陣営にも、サンガララの本陣での戦さの結果がもたらされている頃であろう。
スペイン軍総指揮官ホセ・アントニオ・アレッチェ、あの者のもとに」
強風の中でも、明瞭に響くトゥパク・アマルの低い声が、ビルカパサの鼓膜を震わせた。
ホセ・アントニオ・アレッチェ――その響きに、ビルカパサの指は反射的に腰の帯剣に走り、鞘の上からその重さを確かめる。
一度は捕えたはずのトゥパク・アマルに破獄を許してしまったあの男が、その宿敵を再び目と鼻の先にして、如何なる思いでいることか。
様々な念に駆られながら背後から窺うトゥパク・アマルの輪郭は、激情に燃えているようにも見え、それでいて、恐ろしく冷徹な沈着さを保っているようにも見える。
喉元を唸らせるビルカパサの耳に、再びトゥパク・アマルの低音が響き来る。
「此度の本陣戦、敵軍としては勝機があると思っていたであろう戦いに、思わぬ敗北を喫したことになる。
結果、あのアレッチェ殿の執念に、いっそう油を注ぐこととなった。
いや、アレッチェ殿だけではない。
モスコーソ司祭をはじめ、スペイン軍幹部たちの憎悪をいっそう煽り立てる結果となった。
これから来たるべき彼らとの決戦、我らとしては、なおいっそう心して臨まねばなるまい。
そして、必ずや勝利し、この戦いに終止符を打たねばならぬ。
此度の本陣戦はもとより、これまでの戦いで犠牲となった多くの者たちに報いるためにも――!」

今、光の矢で射抜くがごとく鋭利なトゥパク・アマルの視線の先で、敵の砦の砲門が一つ、荒々しく開け放たれた。
その砲門の陰に、こちらを睨(ね)めつけるアレッチェの姿を垣間見たように思われ、ビルカパサの横顔が野獣の険しさを増す。
これほどの距離がありながらそれはあり得ぬこと、錯覚だと分かりながらも、ビルカパサは、己の全身の筋肉が、主を護るかのように、早くも鋭敏に、熱く高まっていくのを感じずにはいられなかった。
かくして、トゥパク・アマルの予想通り、その頃、彼らの視線の先にあるスペイン軍主力部隊の陣営にも、本陣戦の顛末が知らされようとしていた。
スペイン軍総指揮官ホセ・アントニオ・アレッチェは、砦の一角にしつらえられた彼の執務室で、その胸の悪くなるような報告を受け取った。
「アレッチェ様!!
アレッチェ様!!」
軍服を纏ったまま長椅子で仮眠を取っていた彼は、執務室のドアをけたたましく叩く音に、早朝の薄いまどろみを破られた。
「何事だ?!」
いかにも不機嫌そうにアレッチェがドアを開く。
「ガルベス大佐の副官ナダル殿より火急の伝文でございます!」
「――!」
兵の手に握られた伝文を即座に毟り取ると、その兵の鼻先で乱暴にドアを閉める。
それから、せわしない足取りで書斎机に向かっていく。
まだ内容を確認してもいないのに妙に嫌な予感につかれながら、アレッチェはその報告に目を走らせる。
まだ早朝の薄暗い室内で、アレッチェは忌々しげに机上のカンテラを灯すと、荒々しく椅子を引き寄せた。
それから、改めて伝文を火に近づけ、暗澹と光る黒眼を凝らす。
揺らめく炎を反射する堀の深い顔立ちが、薄闇の中に不気味に浮き上がり、次第に大きく歪んでいく。
と同時に、その眼が、カッと見開かれた。
(あのガルベスが戦死したと?
その上、インカ軍の援軍が多数押し寄せ、我が軍は敗走?!)

暫しの間、呆然と、ナダルの乱れ切った文字を眺めやる。
まるで悪い夢の続きでも見ているような気分であった。
が、ほどなく、アレッチェの中に抑えがたい強烈な憤怒が突き上げてきた。
バンッ、と彼の拳が、雷(いかずち)のごとく机上に叩きつけられる。
「馬鹿な!!
我が軍が負けたなどと……!!」
激しく怒鳴りつけるアレッチェの勢いは、ますます苛烈さを増していく。
「あの陣営の周辺地域には援軍として駆けつけられるインカ軍の戦力は無いと、あれほど調べ上げた上での進軍だったではないか!
インカ軍の援軍が多数押し寄せた、だと?
何を寝ぼけたことを言っておるのだ!!
それとも、トゥパク・アマルが、おまえたちに幻でも見せたと言うのか!!」
一人でいるはずの部屋の奥から聞こえてきたアレッチェの怒声に、彼の側近の一人が、恐る恐るドアの外から声をかける。
「あ、あの…アレッチェ様?」
「煩い!!
下がってろ!!
うすのろめ!!」
いきり立った罵声と共に、ガンッ、と甲走った衝撃音がドア向こうに響いた。
それに引き続く、ガシャンと割れて、床に液体状の何かが飛び散る音。
グラスかインク壷でも投げつけたのではないかと思われるその音に、側近は大きくドアから飛び退った。
「はっ…!
も、申し訳ございません…!」

「クソッ、どいつもこいつもっ……」
そう毒づきながら、アレッチェは床板に唾を吐きつける。
それから、己の感情をいさめようと、憤怒に震える指先を豪奢な葉巻入れに走らせた。
だが、抑えようとすればするほど、噴火口のマグマさながらに煮えたぎる激しい感情は募るばかり。
しまいには、あのトゥパク・アマルが、いかにも不遜な笑みを湛えて己を睥睨しているかのような耐え難い妄想までが、脳裏に侵入してくるありさまであった。
「ええい…!!」
アレッチェは大きく頭(かぶり)を振ると、妄想を叩き出すかのように、己の頭に拳を打ち付けた。
そして、怒りでおぼつかぬ指先で、それでも懸命に葉巻に火をつけ、放心したように椅子にもたれかかる。
(あれほど好条件を整えてやったというのに…!
にもかかわらず、ミカエラや雑魚どもを相手にしてさえ負け戦さとは、何たる恥……!!)
またしても怒涛の憤激が押し寄せ、暗黒色の髪が緋色を帯びてメラメラと宙に燃え上がる。
これでは、副王陛下やモスコーソ様に申し開きのしようも無いではないか!
いや、仮に我が軍が勝利せずとも、せめてミカエラか息子の一人でも捕らえてくることができていれば…!
さすれば、トゥパク・アマルの矛先を鈍らせるために、どれほど役に立ったことか!!)
切歯扼腕しながら、力任せに葉巻を灰皿に擦り付けた。
まだ真新しいその葉巻が、みるみる捻り潰されていく。
「しかし、今さら、何を言っても始まらん…!」
アレッチェは再び拳を机上に叩きつけると、そのまま、それを己の額に押し当てた。
きつく瞼を閉じ、懸命に己の冷静さを取り戻そうと、拳をギリギリと額に食い込ませる。
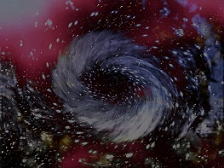
(あるはずの無いインカ軍の援軍の到来――)
アレッチェの耳元に、先刻の己の怒声が甦る。
『それとも、トゥパク・アマルが、おまえたちに幻でも見せたと言うのか!!』
ハッと見開かれた鋭利な眼光が、険しさを増した。
と同時に、黒々とした前髪からのぞくその目が、思慮深げに聳やかされていく。
今、アレッチェの冷徹な思考が、軋みを上げながら、ゆっくりと動き出す。
(インカ軍本陣周辺には、奴らの援軍となりうるような兵力は決して存在しなかったはず。
にもかかわらず、我が軍の兵たちが遁走するほどの大規模なインカ軍の「援軍」が出現したというのは、一体、どういうことだ?
もし本当にそうであったのならば、考えられること、それは……)
彼の獰猛な眼が、殺気を帯びて、血走った閃光を放つ。
(――あのトゥパク・アマルが苦し紛れの策を弄して、それらしく見せかけた、偽装の援軍だったに相違あるまい!
そのような見掛け倒しの小細工に引っかかるとは、何たる…何たる……!)
新たに押し寄せ、激しく燃え上がる、憤激の炎。
その苛烈な炎が全身を焼き尽くして通り過ぎていくのを堪え、待ちながら、アレッチェは二本目の葉巻に火をつけた。
重く濃密な煙を深々と胃の底に落とし込み、懸命に心を鎮め、精神統一しようと試みる。
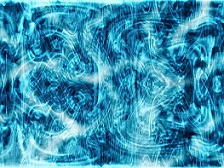
(だが、トゥパク・アマルが何らかの手を打って、本当に「援軍」の幻を見せようと謀ったのだとしても、夜間とはいえ、あのガルベスに鍛えられた我が軍の兵たちが、そう簡単に本物と見誤るだろうか?
もしそのようなことが起こったのだとしたら、その幻を本物と見誤るほどに、我が軍の兵たちが混乱した状況に追いやられていたということになる。
ミカエラや息子たち、そして、訓練の浅い義勇兵たちが大半を占めていたはずのインカ軍の本陣で、何ゆえそのような事態に陥ったのか?)
無意識のうちに、アレッチェの厳つい指先が、苛立たしげにトントンと卓上を弾きはじめる。
静まり返った室内に、その音が妙に大きく響き渡っていく。
彼は、またも葉巻を捻りつぶし、唇を噛み締めた。
(一体、あそこで何があったというのだ……!)
考えれば考えるほど、腑に落ちぬ思いばかりが募りゆく。
「ええいっ!!
あれこれ考えようが、本陣への進軍は失敗に終わったことには変わらぬ!!」
いっそうギリギリと切歯扼腕しながら、立ち上がりざま、椅子を乱暴に蹴り上げる。
「事情は、いずれナダルなり、誰なりに聞き質(ただ)せば知れること。
それよりも、今度こそ、お粗末な失態をしでかさぬことこそが肝要だ」

そのままアレッチェの強靭な足は、猛然たる勢いで、執務室にしつらえられた砲門のひとつへと向かっていく。
そして、大海原に面したそれを無造作に開け放った。
不意に流れ込んできた風に乗って、ツンと強い潮のにおいが顔全体に吹きかかる。
それさえも忌々しげに、アレッチェは顎を反らして、舌を鳴らした。
次第に白みを増す夜明けの空をひとしきり見やった後、彼の視線は自ずとトゥパク・アマル陣営の方角へと動きゆく。
と、その時、アレッチェの横顔で、ハッと、さらに険しく目元が吊り上がった。
かなりの距離があるにもかかわらず、彼方に見張らせるインカ軍陣営の岸壁上に、長身のインディオのシルエットを認めたような気がしたのだ。
(トゥパク・アマル――?!)
しかも、そのインディオは、長髪を潮風に逆巻かせて超然と立ち、微動だにせぬ視線を己の方に据えたまま、射るような眼光をきかせているかのように見える。
忌々しい錯覚だとは思いながらも、アレッチェもまた、その方角を激しく睨(ね)めつけずにはいられない。
獄中からトゥパク・アマルを取り逃がした時の、あの腸(はらわた)が煮えくり返るような憤激までもが甦り、またもや全身が焼け付くようだ。
アレッチェの手が、砲門に据えられた大砲の堅固な砲身を、グッ、と握り締めた。
その冷ややかで強壮な感触を指先で確かめながら、歪んだ口の端から低く冷酷な声が漏れる。
「トゥパク・アマル、本陣戦は上手く切り抜けることができたと、さぞや胸を撫で下ろしていることであろう。
だが、子供騙しの小手先の策が、いつまでも通じると思うなよ。
次なるわたしとの決戦で、本物の戦いというものを存分に思い知らせてやろうではないか。
そして、このような愚かな反乱なぞ、今度こそ完全に叩き潰してくれるわ」

再び、トゥパク・アマル陣営――。
伝令鳥の運んできたミカエラからの報告に目を通したトゥパク・アマルは、一旦、己の天幕に引き返した。
そして、すぐに命じて、本陣戦の結果を今か今かと待ち侘びているであろうアンドレスたち重側近の元に、吉報を知らせる使者を走らせた。
あのアンドレスのことゆえ、昨夜から今に至るまで、己と同様、どれほどの思いで過ごしてきたことか、トゥパク・アマルにも手に取るように察せられていた。
それだけに、勝利の知らせを受け取った彼の歓喜ぶりがありありと想像でき、思わずトゥパク・アマルの目元も緩む。
それから、当陣営の各部隊長たちを早急に己の天幕に参集させた。
隊長たちを前にして、トゥパク・アマルは、劣勢な情勢の本陣に敵襲あれど勝利を果たした、その経過をありのままに伝えていく。
本陣戦の結果がどちらに転ぶか分からぬ状況下では、当陣営の兵たちの不安まで徒(いたずら)に煽ることの無きよう、この件については敢えて伏せていた。
しかし、幸いにも、もたらされたのが勝利の朗報であるならば、その事実と喜びを分かち合うことは、これから厳しい戦いに臨む当地の兵たちにとっても大きな力の源となってくれることであろう。
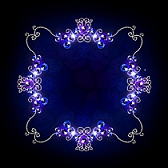
恍惚と歓喜に湧き立ちながら、精悍な面差しをいっそう勇壮に輝かせて己を見上げる兵たちに、トゥパク・アマルも目を細めて、頷いた。
それと同時に、厳粛な口調で言い添えることも忘れない。
「此度の本陣戦の勝利は、誠に喜ばしいことであった。
そして、こうして、その喜びをそなたたちと分かち合えることを、わたしも嬉しく思う。
だが、我らがこれから対峙する相手は一筋縄ではいかぬ者たちであることは、先刻、皆も承知のとおりである。
本陣戦で敗戦を舐めた敵軍は、これまで以上の戦意を燃やして立ち向かってくるであろう。
そなたたちも、そなたたちの配下の者たちも、これからの戦さ、重々その覚悟の上で臨んでほしい」
「はっ!!
トゥパク・アマル様!!」
表情も、身も、凛々しく引き締めて、兵たちは決然と恭順を示す。
そのような彼らに、トゥパク・アマルも「頼んだぞ」と、今一度、力強く頷き返した。
こうして各部隊長たちへの伝達を済ませた後、トゥパク・アマルは、また一人、己の天幕に残り、今度は、素早い手つきで、此度の本陣戦に関わるものとは別の伝文の束を書棚から取り出した。
それは、昨日の英国艦隊とスペイン艦隊の戦況について、マルセラをはじめとした洋上監視部隊が、現地から克明に戦況を知らせてきた数々の報告であった。
海上の伝令用に訓練された伝令鳥によって運ばれてきたそれらの伝文を、手早く、机上に時系列に並べていく。
数十枚にも及ぶ伝文は、布地に記された文字が海水で滲み、触れる指先にも塩のざらつきが感じられる。
それでも、判読できないほどではない。
それらの内容を反芻するように読み返していくトゥパク・アマルの研ぎ澄まされた横顔を、天幕の隙間から差し込む朝の光が静かに照らしている。
こうしている間にも、戦端の切られる時は着実に近づいている――机上の伝文に集中するトゥパク・アマルの表情が鋭さを増していく。
(ベルナルド艦長率いるスペイン艦隊は、戦列艦8隻及び巡洋艦5隻を擁し、対するジョンストン提督率いる英国艦隊は、輸送船を除けば戦列艦6隻と巡洋艦5隻。
数の上では幾分優位であったスペイン艦隊だが、案の定、序盤から、ジョンストンの英国艦隊に圧倒的に押されている)
水平線の彼方から姿を現した英国艦隊の船団が一糸乱れぬ二列縦陣を成し、つまぐるように驀進してくるさまが、そして、緊張を滲ませるスペイン艦隊の船団に容赦無く突撃していくさまが脳裏に浮かび、瞬間、トゥパク・アマルは瞼を伏せた。

(マルセラたちの報告によれば、スペイン艦隊の中に高速で突き進んでいった英国艦隊は、強烈な砲火によって難無くスペイン艦隊の陣容を切り崩し、即座にスペイン艦隊旗艦への猛攻を開始したという)
インカ族の誰もがそうであるように、トゥパク・アマルもまた、戦列艦による海戦の経験など皆無であった。
それにもかかわらず、戦況をリアルタイムに克明に伝えてくる報告文によって、両艦隊の交戦による轟然たる砲撃音や息詰まる硝煙、さらには砲弾が甲板を粉砕する衝撃までもが、臨場感を伴って鮮明に感じ取れる思いであった。
いかに頑強なオーク材で建造された戦列艦とはいえ、そのような至近距離から激しく砲撃し合っては、兵もろとも船体をぶち抜き合い、文字通り地獄絵図さながらの惨状であったに相違無い。
英国艦隊旗艦を率いるジョンストンは、自軍の猛撃に晒されて混乱に陥り反撃の機を掴めぬスペイン艦隊を、そのまま一気に叩き潰さんと狙っていたはず。
殊に、ベルナルド艦長の乗艦するスペイン艦隊旗艦を早々に陥落させ、スペイン艦隊の士気を完全に失墜させようと狙っていたはずだ。
英国艦隊の苛烈な砲撃に見舞われたスペイン艦上――赤々と燃え盛る爆炎と灼熱の煙、落下するマストやヤード(帆桁)の恐ろしい騒音、砲弾が飛び込む度に四囲を震わす轟音、人々の喚声や悲鳴。
それらが再びトゥパク・アマルの脳裏に侵襲し、あまりの生々しさに、船酔いに似た胸のむかつきさえ覚える。
(だが、全てが英国艦隊の思惑通りにいった、というわけではなかった)
トゥパク・アマルは、多数の伝文の中から一枚を選り抜いて、それを手に取った。
(確かに、英国艦隊が圧倒している事態には違いなかったが。
しかし、あの者の策によって、スペイン艦隊は辛うじて反撃の機を掴んだのだ)
切れ長の目元を鋭利に細め、トゥパク・アマルは手の中の伝文を見つめた。
スペイン艦隊旗艦を護るため、英国艦隊の完璧な縦陣を分断すべく、突如、無謀な方向転換を図り、勇猛果敢にも敵艦間に自艦を突っ込ませていった一隻のスペイン艦。

その様子を綴ったマルセラの伝文は、文字も、文体も、驚嘆と興奮に満ちている。
そして、そのスペイン艦を指揮していた人物は、スペイン艦隊副指揮官イグナシオ・フロレス。
このフロレス艦の思わぬ反撃によって、英国側の戦列艦一隻が大破し、戦闘不能に陥った。
さらに、もう一隻の英国軍艦も、フロレス艦の猛攻に屈するところを、すんでのところで逃げ延びたという。
(イグナシオ・フロレス――)
トゥパク・アマルは、伝文の中に幾度も登場するその名を見つめた。
此度のスペイン艦隊を率いるベルナルド艦長の副指揮官として海戦に参戦しているフロレスは、本来は、隣国ラ・プラタ副王領の陸軍に属する将官である。
「スペイン本国生まれでない」というだけで、スペイン生まれのスペイン人から侮蔑の対象とされてきた当植民地生まれのスペイン人であるにもかかわらず、それらの偏見を押し退け、己の実力で最高司法院の議長の地位にまで上りつめた文武両道の人物。

そして、トゥパク・アマルの反乱が幕を開けてからは、副王の命により、ラ・プラタ副王領のインカ軍討伐隊の総指揮官を任じられてきた。
よって、このフロレスは、インカ軍にとって、本来は仇敵にあたるはずであった。
が、トゥパク・アマルにとって、今やフロレスに対する心象はもっと違ったものとなっていた。
ラ・プラタ副王領に遠征していたアンドレスたちは、これまでフロレスと幾度も戦火を交えてきたが、ペルー副王領を拠点に戦ってきたトゥパク・アマル自身は、まだフロレスと直接の面識は無かった。
しかしながら、アンドレスをはじめフロレスと直に接した側近や兵たちから、その人となりや戦いぶりについて、これまでも事細かに報告を受けてくる中で、フロレスに対するトゥパク・アマルの印象は単なる仇敵を超えたものとなっていた。
昨日も、アンドレスの出陣前に海戦の状況について語り合っていた際、アンドレスの口からフロレスの名が出たことが脳裏に甦る。
『トゥパク・アマル様、海戦の状況はどのように?』
『予想通り、英国艦隊が優勢のようだが、スペイン艦隊の一部の艦も奮戦している』
『フロレス殿の艦ですか?』
『そうか。
そなたはフロレス殿と面識があるのだな』
『はい!
スペイン人にも、あのような者がいるのだと、俺の認識を大きく変えてくれた人でした』

トゥパク・アマルは回想から己の意識を引き離し、書棚の一角に置かれた、強壮な戦列艦を模した帆船模型の方を振り向いた。
(フロレス殿は、自艦が敵艦の間で串刺しになる危険を冒してでも、自艦隊の旗艦を護ろうとしたのだ。
幸いにも、敵艦が、フロレス艦の予想を超えた動きに当惑したのか、咄嗟の急回頭によって方向転換を行い、衝突を避けてくれたから良かったようなものを。
そうでなければ、真に、あの者の艦は、2隻の敵艦の艦首と艦尾によって、左右の両側面をもろに貫かれていたはずだ)
深い溜息とも、感嘆の吐息ともとれる息をついて、トゥパク・アマルは、その先の展開が記された伝文へと視線を戻した。
(その上、辛うじて串刺しは免れたとはいえ、敵の至近距離からの容赦無い攻撃によってフロレスの艦は大破して、炎上。
しかし、その火達磨となった自艦を乗り捨てることなく、その艦もろとも、英国艦隊旗艦めがけて突撃を敢行したという。
自らの乗艦を用いて火船攻撃をしかけ、敵旗艦を火災に巻き込み、戦闘不能に陥らせようとしたのだ)

トゥパク・アマルはまた深く息をつくと、伝文を夢中で読み進むうちにすっかり前傾姿勢になっていた長身を椅子の上で正した。
それから、端正な輪郭に垂れかかった前髪を、しなやかな指先でサッとかきあげる。
「フロレス――。
あの者は、本来、陸軍の将官であったがゆえに、かえって海戦の常識を超えた行動に出られたのかもしれぬ。
とはいえ、何という無謀なことばかりする。
このような戦法では、幾ら命があっても足りなかろう」
厳しい声で呟きながらも、トゥパク・アマルの瞳は力を帯びている。
(できることなら、直接、あいまみえてみたかった。
此度の決戦を互いに生き延びたならば、自ずとそのような機会も訪れようが)
トゥパク・アマルは不意に伝文から視線をずらし、天幕の隙間から差し込む朝陽によって長く伸びた己の黒い影に目を落とした。
(だが、フロレス殿、果たして、そなたは今頃……)
湧き上がりかけた感傷を振りほどき、トゥパク・アマルは目を上げる。
彼は、今一度、真直ぐに身を正し、その先の展開が綴られた新たな伝文の束に手を伸ばした。
(火船攻撃を挑んだフロレス艦が敵旗艦の艦尾に激突しかけたところを、相手は首尾よくかわした。
さすがに歴戦のジョンストン提督、そう易々とは、フロレス殿の手には甘んじなかったというわけだ。
が、それでも、炎上したフロレス艦は、敵旗艦の艦尾近い舷側部に接触することに成功。
幾ばくかの損傷と火災をジョンストン艦に被らせた。
フロレス自身は、己の火船をジョンストン艦に衝突させる直前に、炎に包まれた甲板上から部下たちと共に脱出を試み、幸いにも味方のボートによって救出されたという。
――しかし、スペイン艦隊にとっても、また、フロレス殿にとっても、真に厳しい戦いはここからだったのだ)
トゥパク・アマルは、いっそう険しさを増した横顔で、切れ長の目を聳やかせる。
そして、さらにその先の海戦の経過が記された伝文に、鋭い視線を走らせ始めた。
それでは、一旦、我々もトゥパク・アマル陣営を離れ、前日の海戦の舞台へと暫し時を遡ってみたい。
